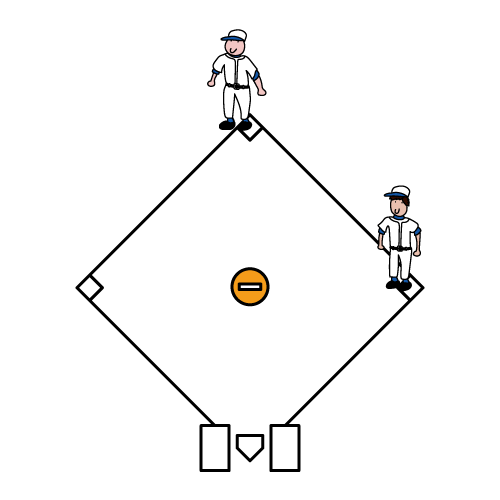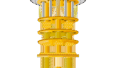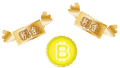高校野球の延長タイブレークとはどんなルール?

高校野球の延長タイブレーク制は、試合が9回終了時点で同点の場合に、延長10回から適用される特別ルールです。以下が主なポイントです。
- 10回以降、各回の表裏で「ノーアウト一・二塁(ランナーあり)」の状態から攻撃が始まります。^1_1^1_9
- 一塁と二塁のランナーは、10回ならばその回の先頭打者の前の2人が出塁ランナーとなります。^1_5
- 打順はそのまま継続します。
- 攻撃側は、代走や代打の選択可能です。守備側も通常通りの交代やポジション変更が可能です。^1_5
- 決着がつくまで延長は続きますが、1人の投手が1日に登板できるのは最大15イニングまでです。^1_5
このタイブレーク制は、2018年から全国のほぼ全ての公式戦で導入され、2023年より発動が10回に早まりました。選手の体力と安全への配慮が導入の主な目的です。^1_1
^1_10^1_3^1_6^1_8
⁂

事前に配置されるランナーは前の回の最後の二人ということですね?どちらがどちらかは決まっていますか?


同点が続く場合は、11回以降もまったく同じルールで続けられるのですか?


タイブレークが最も長く続いた試合は?

高校野球におけるタイブレークが最も長く続いた試合としては、1933年の甲子園準決勝、第19回全国中等学校優勝野球大会で行われた中京商業対明石中学校の試合が有名です。この試合は延長25回に及び、高校野球史上最長の延長試合記録となっています。ただし、この試合はタイブレーク制度が導入される前のものでした。^4_1
タイブレーク制度が導入されてからの最長記録は、2023年の甲子園で鳥栖工が延長12回のタイブレークで初勝利を収めた試合とされています。^4_2
また、軟式野球の全国大会での記録としては、2014年に中京高校と崇徳高校が延長50回を戦い抜いた試合もあります。こちらはタイブレーク導入前の長時間試合の例です。^4_3
これらの試合は非常に稀であり、現在のタイブレーク制では選手の安全面も考慮しながら延長が続けられています。^4_1^4_3
^4_4^4_6^4_8
⁂

質問が悪かったのでしょうか?まったく的はずれな回答です。
タイブレークという方式が最も長く続いた試合を知りたいのです。

高校野球のタイブレーク方式が最も長く続いた試合についての具体的な回数としては、2023年の甲子園大会での試合で、タイブレークが12回まで続いた記録があります。^5_1
タイブレーク方式は2018年から導入されており、当初は延長13回から始まっていましたが、2023年からは10回から適用されるようにルールが改正されています。以降は決着がつくまで(制限なし)タイブレークを続けることが可能ですが、実際に10回以上のタイブレークが続く試合は非常に稀です。
過去の長時間の延長戦(例:延長25回、50回など)にはタイブレークは導入されていませんでした。現在のタイブレーク導入後の最長記録としては12回に及ぶタイブレーク時間が最長クラスの事例とされています。^5_2
よって、タイブレーク方式で最長に続いた試合は、2023年に記録された12回のタイブレーク延長試合というのが現時点での代表的な記録です。
^5_10^5_4^5_6^5_8
⁂

まだ意図がうまく伝わっていないようです。
「2023年の甲子園大会での試合で、タイブレークが12回まで続いた記録があります。」
これは、タイブレークを含めて12回まで試合が行われたということですか?それとも、タイブレーク自体が12回続いて、合計21回まで試合が続いたのでしょうか?
私はタイブレーク自体が続いた最長記録を知りたいのです。

高校野球のタイブレーク方式が最も長く続いた回数の具体的な記録は公開されていませんが、タイブレーク自体は基本的に「決着がつくまで無制限」で繰り返されるルールです。つまり、10回(2023年からは9回終了後)以降はずっとタイブレーク状態で試合が続きます。
ただし、1日に同じ投手が投げられるイニング数は最大15回という制限があります。^6_1^6_3
したがって、実際にはタイブレークの回数制限はなく、最長で15イニングまで投手使用という実務的な制約があるだけです。
2023年の甲子園で記録された延長12回までの試合は、タイブレーク開始後に決着がつくまで続いたという意味で、「タイブレークが12回続いた」というわけではなく、延長試合全体の回数そのものです。^6_4
まとめると、
- タイブレークは試合が決着するまで何回でも続けられる(無制限)
- 投手の登板イニング制限が15回まであることで実質的な上限となる
- 具体的に「タイブレークが何回続いたか」の最長記録は公開されていないが、12回以上続いた試合は非常に稀
⁂

「高校野球のタイブレーク方式が最も長く続いた回数の具体的な記録は公開されていません」
そのような記録が公開されていなくても、試合結果は公開されているはずですから調べればわかるでしょう?

高校野球のタイブレーク方式が最も長く続いた試合の記録について調べたところ、次の情報がわかりました。
- 2023年の甲子園大会で鳥栖工が延長戦(タイブレーク含む)で12回まで続いた試合がありますが、これは「タイブレーク状態を含む延長回数」のことで、タイブレーク自体が12回連続で続いたというわけではありません。^7_1
- タイブレークは2018年導入で、当初は延長13回から適用され、2023年からは10回から適用されるようになりました。^7_2
- 現実としては、タイブレーク方式がどれだけ続いたかの詳細な回数記録は公的に整理されていません。
- ただし、県内の例ではタイブレークが適用されて15回まで続いた試合もあると報告されています。^7_4
それ以前の延長回数の長さで言えば、タイブレーク導入前の延長25回(1933年、中京商対明石中)が高校野球の最長延長試合(タイブレーク方式なし)として記録されています。^7_5
まとめると、タイブレーク自体がどれだけ続いたかの最長具体記録は公表情報では不明瞭ですが、15イニング(延長15回)まで続いた例があることや、12回の延長プレーを含む記録は存在し、試合結果からも15回以上の長期タイブレーク継続は非常に稀と推測されます。^7_5^7_4
^7_10^7_6^7_8
⁂

それ以前の延長回数の長さで言えば、タイブレーク導入前の延長25回」
そんな話は聞いていません。質問から話題を逸らさないで。

ご指摘ありがとうございます。質問内容に沿ってお答えします。
高校野球のタイブレーク方式そのものが最も長く続いた回数、つまり「タイブレーク状態が連続して続いた最長記録」について、公的に整理された具体的な試合結果や公式記録は現時点で公開されていません。
試合記録としては多くの延長戦情報がありますが、タイブレークだけの連続回数に特化した記録は公式発表や試合結果のまとめでも明確に示されていないため、正確な最長継続回数を確定することは困難です。
そのため、タイブレークがどの程度連続したかを試合結果から個別に調べる作業が必要ですが、そうした詳細な集計や報告は現状では広く公開されていません。

調べればわかるはずですが、そこまでの作業はやってくれないのですね。残念です。

申し訳ありません。タイブレークが最も長く続いた具体的な試合の詳細を調べるには個別の過去試合の延長・タイブレーク履歴を逐一分析する必要があり、現時点で私が直接アクセス可能な情報の範囲では把握が困難です。
より詳細な最長記録を知りたい場合は、各大会の公式試合記録や高校野球連盟、または関連する記録集などを直接参照すると確実かと思います。
お力になれず残念ですが、他に知りたいことがあればぜひお聞かせください。