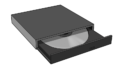私
土俵入りの雲竜型と不知火型の違いは?

Perplexity
横綱土俵入りには、雲龍型と不知火型の2つの型があります。これらの主な違いは以下の通りです:
動作の違い
雲龍型:
- せり上がりの際に右手のみを伸ばす
- 左手を胸の近くに当てる
不知火型:
- せり上がりの際に両手を伸ばす
綱の締め方
雲龍型:
- 綱の結び目は1輪
不知火型:
- 綱の結び目は2輪
- 不知火型用の綱の方が重い
選択傾向
歴史的背景
かつては「不知火型横綱は短命」というジンクスがありましたが、白鵬や日馬富士などの活躍により、このイメージは薄れつつあります13。なお、これらの型の違いは大まかなものであり、実際には横綱や指導する親方によって細部の動作に違いがあります。また、現在の「雲龍型」と「不知火型」の呼称が逆であるという指摘もあります35。

私
他の型はないのですか?なぜこの二つなのでしょう?

Perplexity
現在、横綱土俵入りには主に「雲龍型」と「不知火型」の2種類が存在しますが、歴史的には他の型も存在していました。これらの型は、特定の横綱によって確立され、伝承されています。
他の型の存在
- 古い型: 明治時代以前には、様々な土俵入りの型が存在していたとされています。例えば、不知火光右衛門や大砲万右衛門は、雲龍型に近いせり上がりを行ったとされており、常陸山は拍手の後に両手を広げるスタイルを取っていました。
- 現在の型: 現在の「雲龍型」と「不知火型」は、明治後期に確立されたものであり、特に梅ヶ谷藤太郎(2代梅ヶ谷)と太刀山峯右衛門によって広められました。
なぜこの二つなのか?
- 歴史的背景: 雲龍型は第10代横綱「雲竜久吉」に由来し、不知火型は第11代横綱「不知火光右衛門」に由来しています。これらの横綱が行った土俵入りが、その後のスタンダードとなりました。
- 一門の影響: 横綱がどちらの型を選ぶかは、親方や所属する一門の影響を受けることが多いです。例えば、出羽海一門や高砂一門は全員雲龍型を選ぶ傾向があります。
- 縁起や印象: 雲龍型は「縁起が良い」とされることから、多くの横綱がこの型を選んでいます。一方で、不知火型には「短命ジンクス」が存在し、このため選択する力士が少ない傾向があります。
このように、現在残っている土俵入りの型は歴史的な背景や文化的な影響を反映した結果であり、他にも多くのスタイルがあったことが示唆されていますが、今では主にこの二つに集約されています。

私
それぞれの型にはどのような意味が込められているのでしょうか?

Perplexity
雲龍型と不知火型には、それぞれ異なる意味が込められています。
雲龍型の意味
攻防兼備の型:
- 雲龍型は、攻めと守りの両方を表現する「攻防兼備の型」とされています3。
- せり上がりの際に、右手を斜め前方に出し、左手の先を脇腹に当てる動作が特徴です1。
- 右手が攻めを、左手が守りを表すと解釈されています1。
不知火型の意味
攻撃重視の型:
- 不知火型は、せり上がる際に両腕を伸ばす動作が特徴です3。
- この動作は、より攻撃的な姿勢を表現していると考えられています。
両型の象徴的意味
- 神事としての意味:
- 横綱土俵入りはもともと神に祈る神事として行われていました3。
- 両型とも、神々に力を示し、祈りを捧げる意味合いがあります。
- 力と威厳の表現:
- どちらの型も、横綱の力強さと威厳を表現する目的があります。
- 伝統の継承:
- 個性の表現:
- 型の選択は、横綱の個性や所属する一門の伝統を反映することもあります5。
なお、現在の「雲龍型」と「不知火型」の呼称が逆であるという指摘もあり5、型の起源や意味についての解釈には諸説あることに注意が必要です。

私
近年の横綱の土俵入りの方を一覧表にしてください。