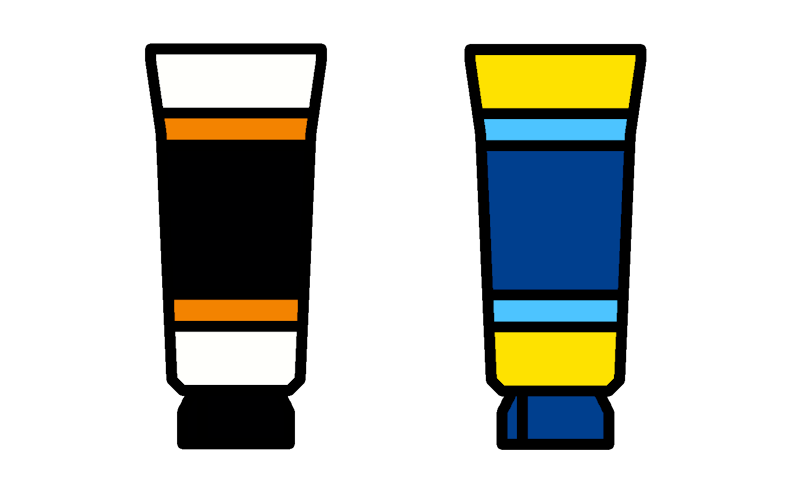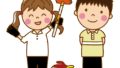エポキシ接着剤がくっつかないものは?

Perplexity
一般的に、エポキシ接着剤がそのままでは「接着しにくい/ほとんどつかない」代表的な素材は次のとおりです。^1_1^1_6^1_9
- シリコーンゴム・シリコーン樹脂。^1_6^1_1
- ポリエチレン(PE)。^1_3^1_1
- ポリプロピレン(PP)。^1_9^1_3
- ポリアセタール(POM、ジュラコン、デルリン等)。^1_1
- フッ素樹脂(PTFE等)。^1_6^1_1
- ナイロン(PA、一部の用途で密着性が弱い)。^1_3
- つるつるした面や強い撥水性・低表面エネルギー表面(前処理なし)。^1_7
ポイントと対策。^1_7
- 表面が低表面エネルギーで撥水性が高いと、エポキシは濡れ広がらず密着が弱くなります。^1_7
- 脱脂と粗面化(サンディング)で密着が改善することがありますが、PE・PP・POM・PTFE・シリコーンはそれでも難しいことが多いです。^1_1
- これら難接着材には専用プライマーや専用品(PP/PE/シリコーン対応接着剤)を使うのが確実です。^1_1
補足。^1_2
- エポキシは多くの素材に強力に接着しますが、混合比や撹拌不良、油分残り、鏡面仕上げなどの条件で「つかない」現象が起きることもあります。^1_4
- 用途に応じて硬化時間や特性が異なるタイプを選定し、取扱説明の混合比・可使時間を厳守することで本来の接着力を発揮します。^1_4
^1_5
⁂

着かない素材を探しています。
例えば、ポリプロピレンの袋などの上に、エポキシ接着剤を付けたものを置いても、容易に剥がせますか?
接着したいものがあり、それが固まるまでに置いておく場所として使いたいのです。

Perplexity
結論として、ポリプロピレン(PP)袋の上はエポキシが極めて付きにくい低表面エネルギー面なので、通常は「固化後に容易に剥がせる一時的な置き場所」として機能します。^2_1^2_3
適材かどうか
- PPやPEは接着剤が濡れ広がらず、一般的なエポキシや瞬間接着剤では密着しにくい代表的な難接着素材です。^2_2
- そのため、PP袋やPEフィルムは養生や作業台の被覆として使うと、硬化後に塊をペリッと剥がしやすいケースが多いです。^2_1
剥がれやすくするコツ
- 表面が清潔で乾燥していれば、油分や粉塵による意図しない“食い付き”や汚染が減り、より剥がしやすくなります。^2_1
- 光沢のあるツルツル面の方が濡れにくく、付着力が下がる傾向があるため、艶ありのPP/PEフィルムが適しています。^2_2
注意点
- PPやPEでも、プライマーや「PP/PE対応」接着剤を使うと付いてしまうため、そうした処理面や製品は避ける必要があります。^2_2
- シリコーン、PTFEはさらに剥離性が高い代表格で、万一エポキシがPPでやや残留した場合は、これら素材のシートを使うとより確実です。^2_2
- 一部の製品では可塑剤や添加剤のにじみで表面状態が変わることがあり、稀にベタつきが残ることがあるため、使うPP/PEシートは作業前に小面積で試験すると安心です。^2_4
代替の養生素材
- シリコーンゴムシートやPTFEシートは、エポキシの離型性が特に高く、硬化中の仮置き・型離れ用に定評があります。^2_2
- 基本方針としては「PP/PE → まず試す」「より確実 → PTFEやシリコーン」とすると、剥離性と取り回しの両立がしやすいです。^2_2
^2_10^2_7^2_9
⁂

ステッカーの剥離紙(ステッカーを剥がした残り)も良さそうでしょうか?

Perplexity
結論として、多くのステッカーの剥離紙はシリコーン離型コートが施されており、エポキシの濡れ・密着が非常に弱いため、硬化中の仮置き用として「剥がれやすい」用途に適します。^3_1^3_3
なぜ剥がれやすいか
- 剥離紙は紙やフィルム基材の表面に離型剤(主にシリコーン)をコーティングし、低表面エネルギー化して粘着剤が付きにくい性質を持たせています。^3_3
- シリコーン離型面は表面張力が非常に低く、上に塗った樹脂や粘着剤が濡れにくいので、硬化後もペリっと離れやすいという特性があります。^3_4
ただし種類差に注意
- 剥離紙にはシリコーン系と非シリコーン系があり、非シリコーン系は離型効果がやや弱い設計のものもあるため、エポキシが薄く広がると一部で密着が残る可能性があります(用途により「軽剥離〜重剥離」まで設定されます)。^3_2^3_4
- 市販ステッカーの台紙の大半はシリコーン系ですが、電子部品用途などでは非シリコーン系が選ばれる例もあるため、手元の剥離紙で小面積テストを推奨します。^3_6
実用上のコツ
- 光沢の強い面(コート側)を上にして使うと離型性が安定しやすいです(片面コートが一般的)。^3_7
- たわみや吸湿で波打つ紙基材より、フィルム系の剥離フィルム(PET+シリコーン等)の方が平滑・耐溶剤性に優れ、エポキシの形保持に有利です。^3_1
- シリコーン転移が気になる工程(後工程で濡れ不良の懸念など)では、非シリコーン系離型フィルムを選ぶと安全です。^3_6
代替案
- PTFEテープ/フィルムやシリコーンゴムシートもエポキシの離型に定評があり、より確実な剥離が期待できます(低表面エネルギー基材)。^3_4
- 目的が「仮置き」であれば、PP・PEの透明フィルムも候補になりますが、剥離紙の方が表面設計が安定しているため再現性は高めです。^3_2
^3_10^3_9
⁂

他に、一般家庭で身近な素材でその目的に良さそうなものはありますか?

Perplexity
結論として、家庭で入手しやすい「エポキシが剥がれやすい」素材としては、シリコーン系のクッキングシート、PTFE加工のベーキングシート、PP/PEフィルム、ステッカーの剥離紙(シリコーンコート面)などが実用的です。^4_1^4_3^4_5
身近でおすすめ
- クッキングシート(表面シリコーン加工):焼き菓子がくっつかないのと同様、低表面エネルギーでエポキシも離型しやすいです。^4_6
- テフロン系ベーキングシート(PTFE含浸ガラスクロス):耐熱・非粘着性が高く、硬化後の剥離性が非常に良好です。^4_2
- PP/PEフィルム(透明梱包フィルム、OPP袋、PE袋):一般にエポキシの濡れが悪く、仮置き用に扱いやすい選択肢です。^4_3
- ステッカー台紙(剥離紙)の光沢面:多くはシリコーン離型コートで、エポキシが乗ってもペリっと外れやすいです。^4_4
使い方のコツ
- 光沢のある離型面(コート側)を上に使うと、より安定して剥がれます。^4_5
- 薄膜のエポキシは端から食い込みが起きることがあるため、フィルムをピンと張る、厚紙に貼るなどで面を平滑に保つと良好です。^4_7
- 高温硬化を伴う場合は、耐熱性が十分なPTFE系や耐熱クッキングシート(〜260℃目安)を選ぶと安心です。^4_8
注意点
- 一部のクッキングシートや剥離紙は非シリコーン系コートのものもあり、離型性が弱い設計の製品も存在するため、小面積で試験してから本番に使うのが安全です。^4_9
- シリコーンの転移が工程に悪影響を与える用途(後工程の塗装・接着など)では、非シリコーン系の離型フィルムに切り替えるとリスクを下げられます。^4_10
代替案
- マスキングテープやクラフトテープのポリオレフィン系表面は簡易離型に使われることがありますが、粘着剤の残留が課題なので養生面としてはPTFEやクッキングシートに劣ります。^4_11
- 長期・繰り返し使用を想定するなら、PTFEシートやPTFEテープは耐薬品性が高く、清掃も容易でコスパが良好です。^4_2
^4_12^4_14^4_16^4_18^4_20^4_22
⁂